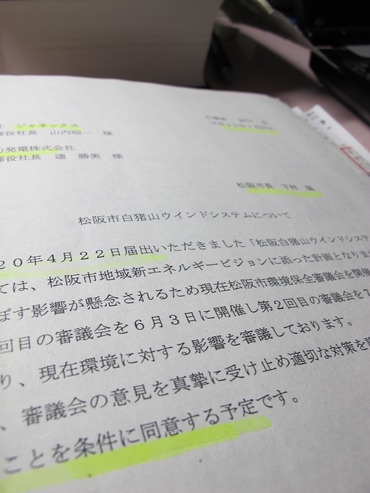松阪市議会議員の海住恒幸(かいじゅう・つねゆき)ブログにご訪問いただき、大変ありがとうございます。
当ブログでは、松阪市の市政や議会で起きていることや起きようとしていることを中心にえがいていくよう努めます。
それは、たんに、日々の出来事を記録するというよりは、事実と、調査研究に根拠を置く「わたし」の目線を入れた分析となるよう、心がけたいと思います。
その結果、地方自治に関する知識をお持ちではなかった方から、「新聞を読んでもわからなかったことがわかった」と言っていただけるようになればと思います。
また、地方自治に関する専門家(研究者)や実務者(自治体職員等)、ジャーナリストの皆さん、議員や首長におかれても必読記事が続出するような質の高さを確保したいと思います。
記事を通して、地方自治、特に松阪市政に、理解と関心を寄せていただくきっかけにしていただければと願います。
国の政治とは異なる、地方自治の意義について、お伝えしたいと思います。
最後になりましたが、地方自治を構成するものは、第一に、住民です。
「見えにくい」と言われる議会や議員の活動を、できるだけ、「見えやすい」ものとなるよう、努めたいと思います。
なお、お気づきの点がございましたら、当ブログのコメント欄やメールにて、お知らせいただければ幸いです。
メール kaiju_matsusaka@ybb.ne.jp
2016年1月4日 海住恒幸