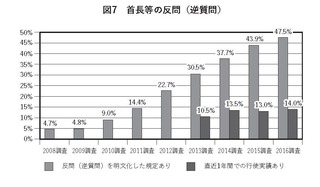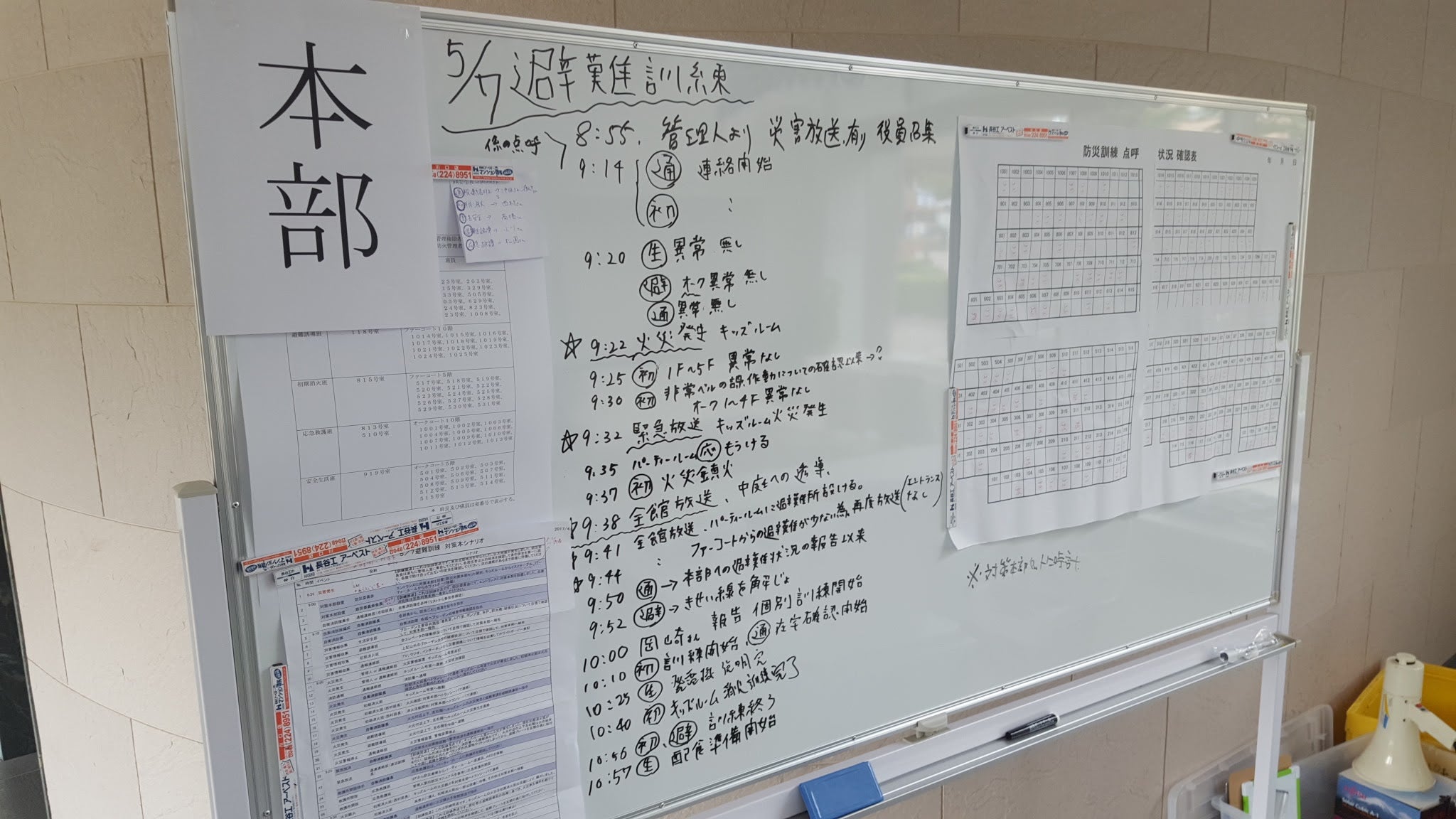水面下の調整で決まりがちな正副議長の選出過程を透明化しようと、事前に名乗りを上げた議員が全議員を前に所信表明演説をする仕組みを導入した宮崎市議会で9日、名乗りを上げず演説もしなかった議員2人がそれぞれ正副議長に選出された。
所信表明は議会内の申し合わせとして2年前に導入されたが、名乗り出なかった議員の選出は初めて。識者からは「議会改革の芽をわずか2年でつんでしまったようなものだ」(畑山敏夫佐賀大教授)との指摘が出ている。
この日は事前に申し出た議長候補2人と副議長候補1人が会議室で全議員に所信を表明した。ただ、その後の本会議では、名乗りを上げなかった無所属の一ノ瀬良尚氏(71)が議長選で18票を獲得。所信表明した無所属の鈴木一成氏(40)と同数となり、くじ引きで一ノ瀬氏に決まった。副議長選も名乗りを上げなかった民進党の郡司敏計氏(70)が最多得票を集めた。
旧清武町長で2期目の一ノ瀬氏は「議長は名誉職。当選回数の多い人からなるべきだと思うが、周囲の要請があり、昨夜引き受けることにした。複雑な心境」と話した。鈴木氏は「議会改革の流れに逆行する。何日も考えてきた演説は何だったのか」と批判した。
=2017/05/10付 西日本新聞朝刊=