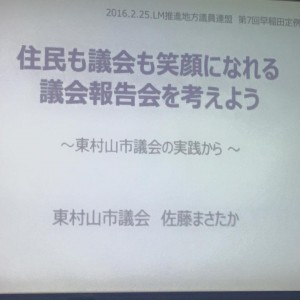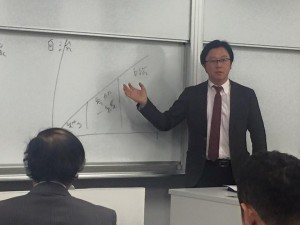<船橋市議のブログより>
さて、先般、議会運営委員会で請願・陳情の取り扱いについての正副委員長案が示されました。
が、その案には私は、漠然とですが納得ができず、態度を留保させていただきました。
なぜなら、過去に勉強したことや、諸先輩から教えていただいてきたこととは相容れないとは言いませんが、それらの理にかなっていない提案だったからです。
なのでまずは地方自治法をしっかりと読んでみました。
第百二十四条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
第百二十五条 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
です。
次に議会運営の解説本を読んでみました。船橋市議会に一番馴染みのある著者の本をそのまま引用させていただきます。
自治省から船橋市に助役としてお越しいただいていた、砂子田 隆 氏編著の「地方公共団体の議会運営」です。渡辺三郎市長の時代だったはずです。著作の発行は、昭和50年7月1日の物です。
以下は、後輩諸氏にお読みいただければと思います。
第8章 請願・陳情
1 請願の意義
請願とは公の機関に対し、その職務に関する事項につき、希望を述べること
をいう。
この制度は、政治上の言論の自由が確立されなかった専制政治の時代には、民意を政治の担当者に知らせるための重要な手段としての役割を演じ、各国の人権宣言にも規定されている。その後、近代的議会制度の発達によって国民参政の途が広く開かれ、政治上の言論の自由が確立されるとともに、しだいにその重要性を失ってきたといわれるが、地方政治の場においては、その活用のいかんによっては、かくれた民意の発掘となるとともに、政治の行き過ぎのブレーキともなる役割が期待されている。
請願は、すでに明治憲法において保障されているが、現行憲法では、何人も、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない旨を規定している(憲法16)。憲法の趣旨に従い、地方議会に対する請願は、法で定められ、国会各議院に対する請願は国会法・衆議院規則・参議院規則で、そのほかの機関に対する請願は請願法で定められている。
請願は、法律的にいえば、単に希望を述べるだけの行為であって、その相手方は、これを受理し、モの職務を執行するうえにそれを参考にしなければならないが、それ以上に拘束されるものではない。しかし、請願はできるだけ尊重するのが請願の趣旨に合するから、地方議会では、これを審査したうえ、採択したものは関係機関に送付するとともに、その処理の経過及び結果の報告を関係機関から請求することができることとしている(法125)。
2 請願権者
普通地方公共団体の議会に請願しうる者は、日本国民のみならず外国人でもよく(昭23.6.16行実)、また当該普通地方公共団体の住民たると否とを問わない(昭25.3.16行実)。現に外国に住んでいる者も請願をなしうるものである。さらに、請願は自然人ばかりでなく法人もその権利を有する。また婦人会、青年団、学校のP・T・A、子供を守る会、労働組合協議会、学校給食会、商店連合会、農業団体などの権利能力なき社団も総代名義またその代表者名義の請願が認められる(昭29.7.26行実、昭38.4.11行実)。ただし、地方公共団体の議会は請願権を有せず(昭28.2.18行実)、とくに市町村の議会が都道府県の議会に請願するという場合は、議会の一般的な対外交渉能力の点からいっても消極に解される。もっともこのような場合、実際には議長名を記載することによって議長個人が請願をした形をとったり、あるいは、陳情書、要望書として取り扱うのが通例である。また、教育委員会、選挙管理委員会、公安委員会、公立学校長などの普通地方公共団体の機関が、1機関として当該普通地方公共団体に請願することはできないと解される(昭27.12.1行実、昭33.2.26行実)。すなわち、これらの機関は、請願の事項を執行すべき側であるから、機関の事務の執行又は手続によって処理すべきことで、たとえ他の機関の権限に具する事項であっても、当該地方公共団体の内部事務の問題として処理すべきものと考えられるからである。なお、公立学校長などが地方公共団体の機関として請願をすることはできないが、住民の1人としてする場合はさしつかえなく(昭33.2.26行実、昭33.5.7行実)、議会の議員も住民としての個人の資格で当該議会に請願することができるものと解される(昭28.4.6行実)。
3 請願事項
請願の対象となる事項は、憲法第16条に、「損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、'廃止又は改正モの他の事項」と規定しているが、原則としてこれらの事項は単なる例示にすぎなく、いっさいの国務又は公務に関する事項に及ぶ。したがって、地方議会に対する請願は、地方公共団体が処理する権限を有する事項のすべてに及ぶものと解される。また、請願者の権利又は利益に直接に関係する事項や、その侵害に対する救済に限られず、直接請願者の利益に関係しない一般公共的事項をも請願の対象となる。ただ、裁判の判決の変更を求めたり、係属中の裁判事件に干渉する請願は、司法権の独立を侵害するものであるから許されないと考えられる。
なお、地方公共団体で処理する権限のない事項についての請願は、これを受理せず請願者に対して正当な官公署を指示して却下し又は正当な官公署に送付するものとすべきであるとする説もあるが、形式・手続が整っているかぎり受理しなければならない(昭26.10.8行実)。
4 請願手続
(1)請願書の提出
請願は、必ず文書によらなければならない(法124)。請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない(標会規(県)88①、(市)136①、(町村)85①)。
(2)議員の紹介
議会に請願書を提出する場合には、議員の紹介がなければならない(法124)。請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない(標会規(県)88②、(市)136②、(町村)85②)。
「紹介」とは、請願の内容に賛意を表し、橋渡しをすることをいう。したがって、同一事項について相反する内容の請願の両者について紹介議員となることはできないと解される。また、請願の内容に反対の議員も紹介議員となるべきでないものであろう。
紹介する議員数は、1人でもさしつかえない。したがって、請願が多数提出されて、その処理に困るという理由で会議規則に例えば紹介議員2人以上を必要とする旨を規定するなどして紹介議員数に制限を加えることは法の趣旨に反する(昭27.、3.13行実)ものと考える。
なお、議長が議員として請願の紹介をすることは、別にさしつかえない(昭32.5.14行実)。
つぎに、紹介の取消しについては、議長が受理し、議会に付託前の請願にあっては議長の承認を得て行うことができる(昭49.2.5行脚)。そして、議会に付託後は、議会の同意を得て紹介を取り消すことになる(昭30.3.18行脚)。また請願の撤回も紹介の取消しと同様に考えられる。そして、会議規則に定めがあれば、それに従うこととなる。
議会に請願が提出され、議会において審議中に紹介議員が死亡し、1人も紹介議員がいなくなった場合でも、議会は、その請願を引き続き審査してさしつかえないと解されている(昭39.7.24行実)。すなわち、議員の紹介は、請願を提出するに際して必要な手続的要件であり、請願が受理されれば、請願書は、その目的を達したものと考えられるからである。
もっとも請願を閉会中に受理後付議するまでに全ての紹介議員がいなくなった場合は、新たな紹介議員を付することが適当で.ある(昭49.4.2行火)。
(3)請願書の提出方法
請願書の提出は、平穏になされなければならない(憲法16、標会規(県)88③、(市)136③、(町村)85③)。この場合の「平穏」の意味は、示威運動や面会の強要等威迫手段によることなくということで、請願文中の文書のいかんは、問うところではない(昭28.9.30行火)。すなわち、請願の提出の手段が「平穏」にということであり、請願の内容がその判断の対象となるものではない。
5 請願の処理
(1)請願の受理
請願は、議会開会中であると閉会中であるとを問わず、所定の様式が整っているものが議長に提出された場合、議長がこれを受理することとなる(昭48.9.25行実)。
また議会に付託するまでの間は、請願提出者は議長の同意を得て、これを取り下げることもできるものと解され、その場合の手続は会議規則に規定すべきである(昭48.9.25行実)。
なお、請願は、当該地方公共団体の権限に属する事項でないと認められる場合においても、さきに述べたように、形式、手続が具備しているかぎり受理しなければならない。
(2)請願の委員会付託
請願は、本会議で審査せず、所管の常任委員会に付託をするのが一般的な扱いで、特別委員会に付託するときは議会の議決が必要である(標会規(県)90、(市)138、(町村)87)。
請願の委員会付託は、常任委員会に対する付託と、特別委員会に対する付託とがある。常任委員会は、法第109条第3項の規定により、その所管に属する「議案・陳情等を審査する」権限を有するから、改めて議決による付託の手続は必要でなく、議長権限で所管委員会に付託することができる。特別委員会は、法第110条第3項の規定により、「議会の議決により付議された事件を審査する。」ので、必ず付託の議決を要する。
請願の委員会付託は、請願文書表の配布によって行われる(標会規(県)90①、(市)138①、(町村)87①)。請願文書表は、請願の要旨を収め、審議の参考に供するために作成されるものである。したがって、付託の内容はあくまで「請願書そのもの」である。
(3)請願の審査
議会が受理した請願を審査するにあたり、それを採択するかどうかは、全く議会の判断にまかせられる。
請願に対する議会の意思決定は採択、不採択の2種しかなく、原則として修正して議決することはない。しかし、請願は請願人の希望に対し、議会が願意に賛意あるいは反対の意を表して採択か不採択かを決するのであるから、便宜的に「趣旨採択」、「一部採択」という方法もとりうる。
採択、不採択の基準としては、まず第1に考慮すべきことは、当該地方公共団体の権限に関する事項であるかどうかである。当該地方公共団体の権限に属しない国際的な問題、国政事務、他の地方公共団体に関する内容のものについては、不採択とするほかはない。第2に、希望の表明が妥当であって、かつ、実現の可能性があるか、少なくとも研究に値いするものでなければならない。
このような基準に基づいて、個々具体的に、採択、不採択を決めるべきものと考える。
同—趣旨の請願がだされている場合は、その一を採択または不採択の議決をしたときでも、他の請願を審議してもさしつかえないが、一括することが適当である(昭28.4.6行実)。
請願に関する議員の除斥については、単に請願の紹介をしたことのみをもって、当該議員がその請願に関する事件に対して除斥されることはない(昭26.3.16行実)。ただし、紹介議員が同時に請願者であったり(昭31.10.31行実)、議員が代表者になっている株式会社の行為が請願事項の対象になっている場合や、あるいはP・T・A会長の職にある議員がP・T・Aに対する補助金交付の請願書を提出する等議員がいわゆる請願事項対象議員であるときは、たとえ請願の内容が一般的、抽象的なものでも、諸般の状況からその事項の内容が客観的に明確に認定されるのであれば、当該議員は除斥される(昭31.10.31行実、昭38.12.25行
実)。
(4)、請願の審査報告
委員会は、付託された請願について、審査の結果を「採択すべきもの」と「不採択とすべきもの」に区分し、意見をつけて、議長に報告する。この場合において、採択すべきものと決定した請願で、長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるものならびにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについてはその旨を付託する(標会規(県)92.(市)140、(町村)89)。
(5)採択請願の処置
議会は、その採択した請願で長その他の関係執行機関において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる(法125)。
関係のある執行機関が、議会の採択した請願の送付を受けた場合には、誠意をもってその処理にあたることは当然であるが、必ずそのとおりの措置をとらなければならない義務はなく、請願の趣旨にそいがたいものについては、理由を付して議会に報告することになる。
6 陳 情
陳情とは、公の機関に対し、特定のことがらについて適当に措置をとってもらうために、その実情を訴える事実上の行為である。
陳情は、請願が憲法に規定された国民の基本的人権の1つとして保証しているのと異なり、特に法律の保護を受けてそのような権利を行使するものではない。陳情を受けた当局側としても、その結果、当然に別段の処理を要求されるものでもない。その手続や形式が別に定められているものでもないが、実態においては、請願とほぼ同様な役割をもっているので、その内容が請願に適合するものについては、請願書の例により処理すべきである(標会規(県)93・(市)142・(町村)90)。
このような趣旨に基づいて、法第109条第3項及び第4項には常任委員会の権限として、「議案、陳情等を審査」し、「予算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開く。」旨を規定している。
http://ameblo.jp/hasegawamasaru/entry-12134621445.html
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2016/03/blog-post_6.html請願・陳情