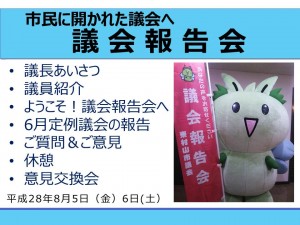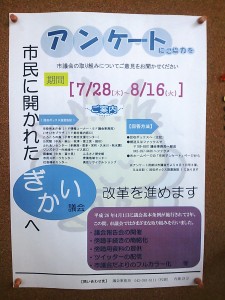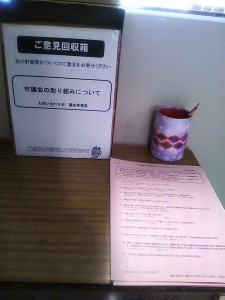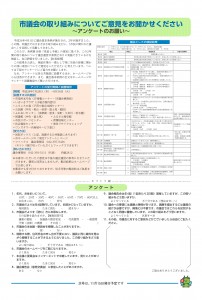初の議会基本条例が施行してから今年で10年。この間、何が変わったのか。課題は何か。これから求められるのは何かをテーマに7月31日に市民と議員の条例づくり交流会議が開かれた。
議会基本条例は2006年に北海道栗山町議会が初めて施行した後、三重県議会などが続き、現在では約800の自治体議会で施行されている。国内の自治体議会数を約1800と考えれば、44%の議会で制定され、武蔵野市議会と同じように現在検討されている議会が制定するとなれば過半数を超える議会で制定されることが見込まれている。今や議会の標準装備とも言える条例だ。
 今回のシンポジウムでは、基調講演として広瀬法政大学教授が、2006年にも議会基本条例をテーマに市民と議員の条例づくり交流会議を開催しているが、当時の資料を基にこれまでの議会改革のポイントと課題について話されていた。
今回のシンポジウムでは、基調講演として広瀬法政大学教授が、2006年にも議会基本条例をテーマに市民と議員の条例づくり交流会議を開催しているが、当時の資料を基にこれまでの議会改革のポイントと課題について話されていた。■二元代表制と議員の意識
簡単にまとめてみると、日本の制度は、首長と議員を選ぶ二元代表制を採用している。ふたつの代表機関がそれぞれに自らの役割、責務を認識して互いに機能すること、慣れ合い、あるいは敵対の関係ではなく、緊張感をもって自治体運営にあたることが前提の制度だが、実際にはどうなのか。議会が政策を作り出すことをせずに首長にお願いしているのではないか。
議会基本条例は、本来の議会の役割は何か、どのように活動するかを明文化し、議会が政策を作ることができることを示すもの。さらに、とかくブラックボックスだった議会に風穴を開け、二元代表制を機能させる大きな改革につながったとされていた。
しかし、一方で制定しても何も変わらないとの声も少なくない。そこには、制度は作っても、首長中心主義、言い換えれば首長にお願い主義が議員意識に根付いており、ここが変わらないから二元代表制が機能しないのではないか。これは住民も同じなのだろう。そう考えると、議会基本条例を作ることだけがゴールではなく、議員の意識改革が最も大切であることを再認識したものだった。
■議会の役割
良くあることだが、選挙で首長が変わると政策ががらりと変わることがある。有権者も求めているのかもしれないが、それで良いのかの問いかけもあった。首長が変わったら、政策ががらりと変わると議会は何をしていたのか。民意を反映していたのかとなるからだ。
議会はチェック機関と言う議員は多いが、それだけで良いのか? ということだ。
議案が提出され、質問はするものの、結果的には賛成多数で可決されていくだけというケースは、武蔵野市議会に限らず多くの議会の実情だろう。これでは首長が全てを考え、決めて、執行していくことになる。議会は何をしているか分からないと多くの人に言われるが、そのことがこの流れに象徴されている大きな課題だ。
議会基本条例を各地の議会が制定するなかで、真の二元代表制の一翼となる議会になるためこの課題へ議会自らが仕組みを作ってきている議会が出てきている。
例えば、三重県議会基本条例では議会に付属機関を置き、議会がより調査をできるようにしている。他の議会でも、行政計画を議決対象にする(議会が議決しないと計画が策定できない)など首長任せではなく議会が主導権を握る動きが出てきている。
さらに、審議をより深めるためには時間が必要となり、年に四回の議会を開催するのではなく、一年中開催する通年議会の制度も広まっている。
議会基本条例を制定するだけでなく、条例でどのように議会活動をより高めるかが示せている例だ。
 ■議会は何をするところ
■議会は何をするところ■討論の広場
この日には、栗山町議会、会津若松市議会、三重県議会から議会改革の実践についての報告もあった。内容については、すでに知っていたことだが、あらためて聞いて印象深かったのは、議会の審議のあり方だった。
それは、論点・争点を明確に出来ているか、討論の広場となっているかの論点だ。
討論の広場とは、栗山町議会基本条例に『議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な討議をとおして、これら論点、争点を発見、公開することは討論の広場である議会の第一の使命である』と書かれていることで、議会審議の本質を示している言葉だ。
知らないことを質問しているようでは、そんなことは知っているよ、とか、電話で聞けと言われてしまい、議会の存在意義を低くしてしまうことになる。どこに問題点があり、選択肢に何があるか。どうすれば、より住民になるのかをその場で明らかにできることになる重要な審議手法だ。このことが示されたうえで議決がされれば、結果に納得する住民が増え、議会の存在意義を高めることになるものだ。
議会とは何をするところなのかの問に対して答えの一つだろう。議会基本条例の制定や議会改革を進めたことで実現ができているかが、問われていることになる。
(続く)
http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52466669.html