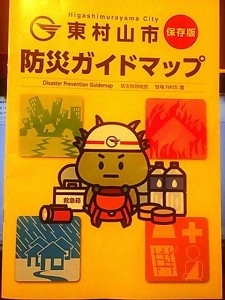<東京財団メールマガジンより>
議会基本条例10年シンポジウム(東京財団主催/河北新報社共催)
~「東北から問う 地方議会の現在・過去・未来」~
2006年5月に北海道栗山町議会が制定した全国初の議会基本条例に始まる議会改革は、着実に成果を挙げ、この10年で800近くの自治体議会が基本条例を制定、運用しています。
その一方で昨今、政務活動費の不正受給が相次ぎ、地方議員、地方議会の存在意義が問われる事態となっています。また、人口減少による財政縮小で行政サービスのかじ取りは今後ますます難しくなることが予想され、議会の役割、意義も極めて重大になることは言うまでもありません。
東北地方最大の都市・仙台で開催するシンポジウムでは、議会基本条例「東京財団モデル」が必須3要件とした(1)議会報告会・意見交換会、(2)請願・陳情者の意見陳述、(3)議員間の自由討議 ― を軸に、基本条例の原点と意義をあらためて確認し、今後の議会改革の方向性、市民参加のあり方を議論します。お誘い合わせの上、ご参加ください。
【日時】2016年11月26日(土)13:30~16:00 (開場13:00)
【会場】河北新報社1階ホール(宮城県仙台市青葉区五橋1丁目2-28)
【テーマ】「東北から問う 地方議会の現在・過去・未来」
【パネリスト】*はコーディネーター
江藤俊昭(山梨学院大学法学部政治行政学科教授)
廣瀬克哉(法政大学法学部政治学科教授)
中尾 修(東京財団研究員(元北海道栗山町議会事務局長))
福嶋浩彦(中央学院大学社会システム研究所教授(元千葉県我孫子市長、元消費者庁長官))
千葉茂明*((株)ぎょうせい 月刊『ガバナンス』編集長)
【プログラム】
13:30-14:30 パネリスト、コーディネーターの報告
14:30-14:40 休憩(質問票の回収)
14:40-16:00 パネル討論(含質問への回答)
【定員】120名
【参加費】無料
▼ お申し込みはこちら
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2016/11/10.html議会基本条例10年シンポジウム(東京財団主催/河北新報社共催)