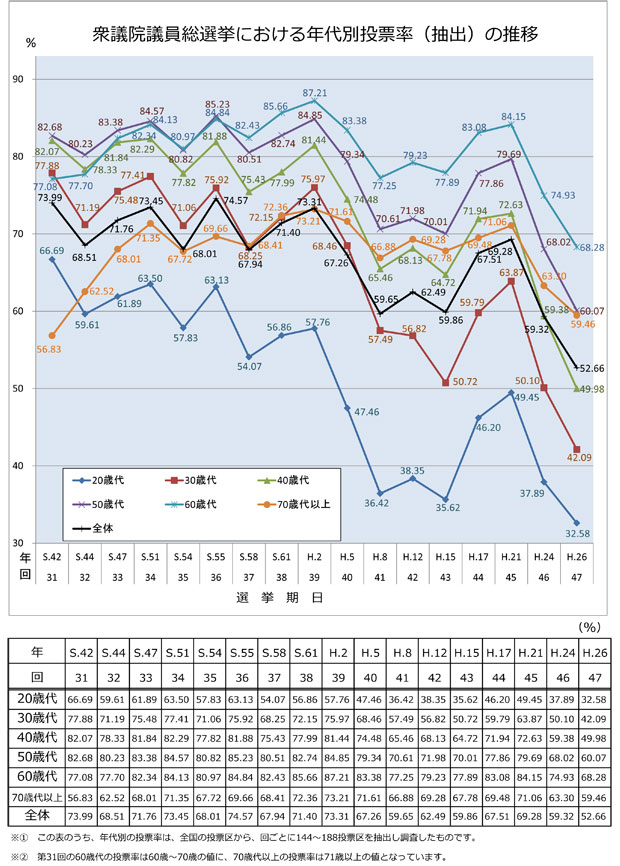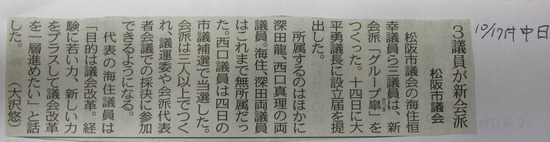<松坂市議のブログより>
わたし、海住恒幸は、2003年(平成15年)春、松阪市議会議員に初当選させていただいて以来、議会内の会派に属さないかたちで議員活動をしてきましたが、このたび、松阪市議会の会派を設立する届けを議長に提出しましたのでお知らせします。
本日、常任委員会終了後に開かれる会派代表者会議で議長から報告があります。
会派名 グループ皐 (読み方・ぐるーぷさつき)
☆会派名の意味
「皐」という文字の語源には、水辺に開かれた平ら(フラット)な地との意味があり、個々の議員として新しい展開を見ようとする関係性を表しました。
メンバー 3人
海住恒幸 (2003年4月初当選、当選回数4回、56歳)
深田 龍 (2013年7月初当選、当選回数1回、35歳)
西口真理 (2015年10月初当選、当選回数1回、56歳)
代表 海住恒幸
☆以下は、3人のメンバーでおこなった意見交換をベースにまとめた会派としての方向性についての海住私案です。
会派を作る目的 議会改革
これまでの経験に、若い力、新しい力をプラスして議会改革を一層進めます。
議会改革とは、市民が議会を見て納得できる状態にある議会にすること。
(審議力、質問力、決め方、見てもらい方、説明力、市民の意見の聴き方等々)
→ 二元代表型議会の機能の完全化
議会みんなで議論し、議会全体の審議力を高め、市民のための議会づくりにつなげていきたいと考えます。
そんな議会にしていくための原動力として会派を機能させていくことが、会派設立の意義であると考えます。
●メンバー個々と会派の関係
・メンバー個々の関係はフラットなものとします。
・メンバー個々が、どの政党にも属さず、市民目線に立った議会活動をしていきます。
・メンバー個々が議員として力を発揮できるよう、会派として研修活動をしていきます。
・メンバーお互いが市政について幅広い情報収集力と調査・分析力を身につけることで、会派としてこれからの市政の展開を見通した政策を議会や市長に提言できるよう努めます。
・議会提出議案に対する賛否の判断は本人の意思に委ねますが、会派として十分に調査・研究、議論に努めます。
●会派として
・会派として議案の調査・研究に努め、議会の審議機能の向上に寄与したいと考えます。
・会派として研究テーマを用意し、他会派等の議員にも参加していただける勉強機会を設けたいと考えます。
・市民が地方自治並びに議会に関心や知識を持てるような勉強機会をつくります。
・市長に寄るのでも距離を置くのでもありません。市長がだれであるかではなく、議案の内容で賛否を判断します。
・何が市民の利益にかなうかを基準に、一人ひとりのメンバーが判断できる資質を身につけ、絶えず議員力を向上していけるよう、研修に力を入れます。
●議会改革を前へと進めます。
・市民も議員ともに「議会は市民のもの」であるという意識を持てるような議会づくりを目指していきます。
・審議機関としての議会の活動を市民により見えやすくするための研究や提言を行っていきます。
・議決機関としての議会の責任を果たすため、審議過程(審議力の向上・審議過程のわかりやすさ・審議過程の中への市民意見の集約機能)を改革するための研究や提言を行っていきます。
・年中活動する議会づくり
●議員報酬や定数について
・議員報酬や定数については、市民や有識者等がその決定に参加できるよう市民に開かれた第三者機関での調査・研究・検討を踏まえて決定できる方向に道を開くものとします。
概ね、上記の事項は、わたし自身、かねてより膨らませていた、これからの議会づくりへの構想を含むもので、松阪市議会はもとより、県内外の議員、市民とも共有したいと考えていました。それらを実行に移す第一歩として、会派設立に踏み切る決意をしました。
わたしは、議員になって以来、会派を不要とする立場をとり、会派には入らないとしてきました。
わたし一人では、それでも構わないし、この12年のあいだに議会基本条例もでき、その検討の過程の段階から無会派の立場でも参加することで議会改革を推し進めてきました。その結果、会派に入らなくても、議員個々の質問時間に差異がないなど、ほとんど不自由のない議員活動ができる状況になってきました。
一方で、その間、従来、弊害ばかり目立った会派という存在も、議会機能を高めるツールとして機能し得る状況となってきました。
また、2年前に深田龍くんが議員になって以来、深田くんからは、つねづね、「会派をつくってもらえませんか」と言われ続けてきました。
わたしも、ことさら、会派に入る無しにこだわることに意味を感じなくなりつつありました。
「作るなら、「政策集団『響(ひびく)』はどうか」と、冗談で逆提案をしたこともありました。
さまざまな市民の方からも、「一人でやるよりも・・・」と言われ続けてもいます。
そんなこともあり、今回は、わたしのほうから、「会派を作ろうか」と話を持ち掛けました。
その提案を待っていてくれたようでした。
会派のネーミングは、深田くんの提案です。
わたしは、議員歴12年と6か月となり、ちよっと数えたら、現在の定例会でちょうど50回の定例会を迎えていました。初当選以来、すべての定例会で一般質問をしていますので、その回数も50回となりました。
まあ、ここまで一人でやってきたのだから、途中で折れたわけではなく、議会活動を進める段階をクルマのギアにたとえるなら、「議会と闘う」ことを宣言した「ロー」(1期)、「セカンド」(2期)の時代から、議会改革検討委員会や議会改革特別委員会の作業部会で朝から晩まで激しい議論を交わした「サード」(3期)までシフトしたそのあと、いっきに「トップ」(4期)ギアにシフトし、その走りを全開させていただいても許される段階に入ったのではないでしょかという思いもあります。
今月5日の議員補欠選挙で当選したばかりの議員もいます。
そこで、「これまでの経験に、若い力、新しい力をプラスして議会改革を一層進めます。」
一人で何も支障のない議会にしてきたつもりではありますが、より大きな責任を果たしていくために、メンバーそれぞれのフラットな関係性をベースにした会派をつくることにしました。
いましなければならない課題を解決し、さらに、「議会を市民のもの」にしていくための必要な手だてを打っていく、そんなグループにしたいと思っています。  http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52229096.html
http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52229096.html
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2015/10/blog-post_20.html会派「グループ皐」を設立します