<船橋市議のブログより>
なんとなく夏休み気分で仕事以外の話をブログに書いていましたが、仕事の話に入りましょう。
前にも書きましたが、私は、今、山梨学院大学大学院といっても夜学ですが、社会科学研究科に通っています。行ってみてよかったなと思うのは、まず指導教授は議会改革等で業界的には第一人者の江藤俊昭先生。
そもそも議会改革学者(そんな学者は本当はいない)の先生方っていうのは実は実態を無視した学術論でくるので、私はこのブログでも批判的でした。
ところがある講演を聞いて、こりゃ行くっきゃないなと思って、その門を叩きました。
予想以上にすごいのです。
現場の事情を恐ろしいほど知っている先生なのです。先生以外に地方議会論的なことをやっていらっしゃる先生は、あとお二人ですが、その先生方は現場無視に近い感じです。
そこで育った議員が身近にいますが、規範論というかあるべき姿(理想論)だけを追っている感じです。それでは現場の現実とのギャップがありすぎて、その差を埋めきれません。
そんな中、講義の度に議論が深まる授業は楽しくて仕方ありません。
とは言え、卒業単位が必要ですから、他の授業もあるのですが、遠路ですから、夏季にまとめて集中講座をやって単位取得をさせていただけます。
そこで受けた授業がこれまたすごいのです。
一つは、社会保障法特殊講義。厚生労働省のOBですが、法制の参事官などをお務めになった方で、非常にわかりやすく現場(地方)のことを絡めながらの講義でした。
二つ目は、地域経営論特殊講義で、これは元多治見市長だった方。まさに実践を通じての講義。
三つ目が、憲法。なのに、地方行政に関わる部分や今、旬な話題を交えながらの講義。
そこでわかったのが、社会人をやって、それなりの経験をしてこないと、というか、もっと言えば、議員とか公務員とかで職務経験がそういう人たちに特化した授業構成になっている感があります。
私は全てが合点が行くというか、今まで、モヤモヤしていたことが理論的に説明していただき、役所仕事でなんとなくわかっていたことがはっきりとわかった感があります。
昨今の、社会人枠のある大学院や大学は、私も色々と調べましたが、ぴったりくるものがありませんでした。
明治大学のガバナンス研究科や拓殖大学地方政治行政研究科、法政大学大学院などが我々議員向けがあるのですが、いまひとつ学歴ロンダリングの感が否めないんですよね。っていうか、あくまでも公務員向けで議員向けとしては講座が少ないのではないかという感じ。
どこも、公共政策中心ですから、ある程度公務に関する職務経験を有していないとついていけないのではないかと思うんですよね。
私のところは、車飛ばしてでも行く価値ありって感じで楽しくやっています。
そんな中、今回、広域連携を考える研究会があり、行ってまいりました。
学者かぶれになるなよと言われそうですが、はいはい大丈夫。現場に軸足を置いているからこそ成り立つ勉強です。(笑)。
で、合併が一段落して、次は広域か?って思いましたが、いやいや違っていて、なるほどなあ~でした。
まあ、最初に3大都市圏は無理よって言われたので、他人事として冷めた目で聞いていましたが、面白い。というか切実。
北杜市の事例発表があって驚き。何が驚きかって、現市長って知ってる人でした。
議長の時に、山梨県議長会長として会議や意見交換会で隣同士になってよくおしゃべりした議長でした。もうそこそこのおばさまだったので、説明を受けて当市初の女性市長です。って言われた時に「ん?」と思って、すぐに検索をかけたら、あ~、あ~この人だ~って。(笑)すごいなあ~。
で、その話はさておいて、広域連携です。
出てきた言葉が「定住自立圏」構想。
で、事例発表では、八ヶ岳の街なんですね。北杜市って。で、県境を越えての広域連携をしている話でした。
北杜市定住自立圏構想(左をクリックしてください)
参考までに、市長の部屋(左をクリックしてください)
で、総務部地域課長さんの説明だったのですが、まあ、流暢に説明いただいて立て板に水でした。質問を受けても全て答えられるって感じでした。
内容はお読みいただくとして、どこも必死なんですよ。人口減。税収減。どうやって街を維持して行くか?です。大変ですね。
他は大変ですね。などというと、うちはうちで、これまた悩みは多いんですよって聞こえてきそうですけど、いやいや必死さはないよな。って感じ。まあ、なんとかなるべ。みたいな。感じ。
でも広域連携ってちょっと興味持ったかなと。
これ気をつけないと、過疎が進む地方をバカにしていると、あっという間に抜かれちゃうんじゃないの?って思います。
この定住自立圏構想って、近隣で話し合って、うまく機能分担をしようという話。
余生は都会を離れたところでと考える方々が増えてきて、現役世代が3大都市圏に住み、リタイアしたら、とりあえず都会の喧騒からは離れたいと考える人たちが増えてくれば、それなりの政策転換がなされてくるわけで、そうしたら、国の施策や、税の配分のあり方が変わってくるのではないか?と思うのです。
冷静に考えたら、地方を殺すわけにはいきませんものね。
もう少し別の角度からも考えてみたいのですが、ちょっと気になる地方の様子でした。
http://ameblo.jp/hasegawamasaru/entry-12301685625.html
議会が本来あるべき役割や機能を果たす為に必要な条例を制定し、改革を進めて欲しいとの想いから市民有志が集い、立ち上げた「議会基本条例を考える会」の公式ブログになります。 川口市を中心に埼玉県内自治体に関する活動・情報等を掲載していきます。 http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/より移転しました。 ※スマホ版は▼から各種メニューを選択できます。
2017年8月19日土曜日
2017年8月18日金曜日
7/30 議会改革の原点
<朝霞市議のブログより>
29~30日、2007年に議会改革の号砲を鳴らした「市民と議員の条例づくり交流会議」に運営者側として参加してきました。
今年は、議会のチェック機能が働いているのか、というテーマでした。都議選でも、前の巨大与党に変わる、新たな巨大与党が誕生しているなかで、改めて議会が行政をチェックするということは何かということを考えたいというテーマ設定でした。
1日目の29日
・全国の議会改革の進展を調査速報から確認し、情報公開や一般質問の改革は進んでいるものの、議員立法はまだまだ、市民が議会に関わる仕組みづくりは立ち後れていることが報告されました。
・その後、自治体の監査委員のうち1人が議員から選ばれている制度がやめられる仕組みが導入され、議員選出の監査委員にどのような効果があるのかという議論がされました。行政職員出身の委員は、否定的な意見をする一方、議員として監査委員を経験した登壇者は、議員が行う監査は単なる会計的なチェックにとどまらず、筋のおかしな話を発見したりする効能がある、というような対論が行われました。
私は、監査委員のうち1人を議員とすることには懐疑的です。現在は市長の指名・任命となっており、議会のなかでの力関係が中立的になって事実上の指名権を議会が握らない限り、市長の都合の悪いことをチェックする人を市長が選ぶという構造になることや、専門性や職務の中立性、先入観がなく監査できるかというと心許ない感じがしています。
2日目の30日
・午前中は分科会。私は新公会計改革の運営を担当しました。今年度から自治体は貸借対照表を作ることになり、企業感覚の導入という言葉に表面的に共鳴する人には萌え萌えの改革が始まりますが、実態としては、過剰な資産の価値を維持するために膨大な減価償却費と維持費を毎年計上しなければならない、というよくわからない状況が出てきます。一方で、公共施設の年あたりの維持費用などが明確になったり、公共施設の無秩序な要求をセーブできるデータが出てくる期待も感じられます。
・午後は、各分科会の報告でしたが、議会への若者参加を取り組んでいる高島高校の取り組みが注目され、その報告に対する質問や討論で埋め尽くされました。若者の政治参加意識が低くて、教育、教育と言われますが、表面的な知識注入やモラルの押し込みではなく、子どもたちが地域社会に参加して、ルールや秩序や利益配分を変えていく体験をしなければ難しく、そのよい機会を議会が形成できるか問われているのだと思いました。
http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2017/07/730-2460.html
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/08/730.html7/30 議会改革の原点
2017年8月17日木曜日
今度の議会改革検討委員会は「公開」で。ムダ使いの廃止や透明化、住民参加を目指して
<BLOGOSより>
こんばんは、都議会議員(北区選出)のおときた駿です。
昨日のブログにおいて、「議会改革検討委員会」が全会一致で設置されたことを簡単に述べましたが、こちらは非常に重要な動きなので、改めて取り上げておきます。
都議会、議会改革は公開で議論へ
http://www.sankei.com/politics/news/170808/plt1708080007-n1.html
都議会が新たに設置、議会改革検討委員会 委員長には都民ファースト木村氏
https://thepage.jp/tokyo/detail/20170809-00000006-wordleaf
これまでも都議会には、議員報酬や議員定数などを議論する場として「都議会のあり方検討会」という会議体が存在していました。
しかしながら、この会議体はすべて非公開で行われており、また少数会派は参加することができませんでした。
参考:セクハラやじ問題総括・費用弁償の是非等を協議する「都議会のあり方検討会」は、原則『非公開』が決定…
http://otokitashun.com/blog/togikai/8841/
上記の過去記事でも言及した通り、「非公開」という場では外部からのプレッシャーに晒されませんから、議員たちは保身に走りがちになり、自分たちが痛みを取る「身を切る改革」は先送りにされがちです。
加えて、発言が公開されなければ責任を問われませんから、「我田引水」な主張や議論の誘導も可能になります。
そして実際、非公開であるのを良いことに、定数是正においては「2増2減」という極めて不可解な決定が行われ、それを主張した会派や議員などが、充分な説明をすることはありませんでした。
参考:北区で一番有名な無職になることが確定??都議会議員の定数が狙い撃ちで4→3に減らされた意味
http://otokitashun.com/blog/togikai/11750/
まあこの時、本来定数が減らされるはずだった区を外し、北区を定数減とした結果、それを主導した会派の方が落選してしまったのは皮肉な結果となりましたが…。
このような結果も踏まえて、今回新たに設置される検討委員会は、原則として「公開」となっています。この検討会の場で、都民ファーストの会は選挙で皆さまにお約束をしたことの実現を図っていく次第です。
委員会構成でも、一人会派まですべて入れることはできませんでしたが、複数人会派からはすべて委員が選出されており、この点でも改善が見られるのではないかと思います。
鈴木 邦和 @kunikazu_suzuki
昨日の都議会にて公営企業委員会への所属が決まりました。仲間と共に満員電車の対策や、上下水道の整備に取り組みます。
そして、議会改革検討委員会にも選出頂きました。議会改革は私が最もやりたかったテーマ。情報公開、住民参加、議論の活性化などを軸に、新しい地方議会の形を作ります。
都民ファーストの会からは、役員が中心となって選出されたメンバーに加えて、「議会改革の鬼」とも言えるほど当選前からこの分野に燃えていた期待の新人、鈴木邦和都議なども委員に入り、活発な議論や提案が行われることが期待されるところです。
私も積極的に委員会を傍聴し、皆さまに改革の進捗をお知らせしていきます。
それでは、また明日。
________________________________________
ここまで書くか!?
誰も語れなかった「不都合な真実」を、
現役議員が赤裸々に明かす。
「東京都の闇を暴く」
おときた駿 プロフィール
東京都議会議員(北区選出)/北区出身 33歳
1983年生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、LVMHモエヘネシー・ルイヴィトングループで7年間のビジネス経験を経て、現在東京都議会議員一期目。ネットを中心に積極的な情報発信を行い、日本初のブロガー議員として活動中。
著書に「ギャル男でもわかる政治の話(ディスカヴァー・トゥエンティワン)」、「東京都の闇を暴く(新潮社)」
http://blogos.com/article/239935/?p=1
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/08/blog-post_17.html今度の議会改革検討委員会は「公開」で。ムダ使いの廃止や透明化、住民参加を目指して
2017年8月16日水曜日
議会を夜間・休日に開催へ 長野・喬木村、なり手確保
<YAHHOニュースより>
長野県喬木(たかぎ)村議会(定数12)が、議員のなり手を確保するため、主な議会日程を原則として夜間・休日に開く方針を決めた。総務省によると、傍聴者を増やすために数日程度、夜間や休日に開く例はあるが、夜間・休日を原則とする議会は全国で例がないという。仕事を続けながら議員活動をできるようにする狙いだ。
人口約6千人の喬木村では6月の村議選が8年ぶりに無投票になった。定員割れへの危機感が高まり、村議の全員協議会でなり手確保の改革について話し合い、若い現役世代が議員になれる環境をつくろうと、原則として夜間・休日開催にする方針を決めた。
今月から、すでに議員全員協議会を夜間に開く試みを始めており、今年の12月定例会から一般質問を休日に、常任委員会を午後7時から実施する方針。答弁する側の村職員の労働環境も変わるため、村職員でつくる労働組合と協議し、合意が得られれば実施する。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170809-00000107-asahi-pol
長野県喬木(たかぎ)村議会(定数12)が、議員のなり手を確保するため、主な議会日程を原則として夜間・休日に開く方針を決めた。総務省によると、傍聴者を増やすために数日程度、夜間や休日に開く例はあるが、夜間・休日を原則とする議会は全国で例がないという。仕事を続けながら議員活動をできるようにする狙いだ。
人口約6千人の喬木村では6月の村議選が8年ぶりに無投票になった。定員割れへの危機感が高まり、村議の全員協議会でなり手確保の改革について話し合い、若い現役世代が議員になれる環境をつくろうと、原則として夜間・休日開催にする方針を決めた。
今月から、すでに議員全員協議会を夜間に開く試みを始めており、今年の12月定例会から一般質問を休日に、常任委員会を午後7時から実施する方針。答弁する側の村職員の労働環境も変わるため、村職員でつくる労働組合と協議し、合意が得られれば実施する。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170809-00000107-asahi-pol
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/08/blog-post_16.html議会を夜間・休日に開催へ 長野・喬木村、なり手確保
2017年8月15日火曜日
松阪市議会の体制づくり
<松坂市議のブログより>
7月の選挙で新しい議員構成となった松阪市議会は、9日、議長選を行うなど、これから1年間の体制づくりをしました。
議長選、副議長選は、議会基本条例に基づいて、立候補者による所信表明と質疑応答を行うこととしております。これは、以前、密室非公開の会派代表者会議で各会派の意向を調整し合う中で実質、議長、副議長を決めていたのをやめるため、議会改革の議論の末、実施を決めた仕組みです。
とはいえ、候補者が出そろった段階で、議長、副議長は事実上決まっているのが実態であることには変わりなく、せめて、こうした状態に抗したいと、これまでに2度、議長選に、そして、今回は副議長選に立候補しましたが、またしても敗れてしまいました。
制度としては決定過程をオープンにしたいと思い、現在の仕組みを作りましたが、候補者への質問も出ないありさまです。
ただ、これにあきらめることなく、思いつく限りの試行・チャレンジでわたし自身の改革エンジンは止めないようにしたいと思います。
街を歩けば、ほんとうにたくさんの市民の方々が、「頑張ってほしい」と笑顔を向けてくださいます。
現在の議会状況と、市民の皆さんの期待とのあいだにはズレが大きすぎるところがあり、わたしが選挙で掲げた議会改革の内容の実現はほんとうに困難な道のりであると感じずにはいられませんが、市民の方々の笑顔はほんとうに励みとなります。頑張り抜かなければならない決意にしていただけます。
http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52277766.html
7月の選挙で新しい議員構成となった松阪市議会は、9日、議長選を行うなど、これから1年間の体制づくりをしました。
議長選、副議長選は、議会基本条例に基づいて、立候補者による所信表明と質疑応答を行うこととしております。これは、以前、密室非公開の会派代表者会議で各会派の意向を調整し合う中で実質、議長、副議長を決めていたのをやめるため、議会改革の議論の末、実施を決めた仕組みです。
とはいえ、候補者が出そろった段階で、議長、副議長は事実上決まっているのが実態であることには変わりなく、せめて、こうした状態に抗したいと、これまでに2度、議長選に、そして、今回は副議長選に立候補しましたが、またしても敗れてしまいました。
制度としては決定過程をオープンにしたいと思い、現在の仕組みを作りましたが、候補者への質問も出ないありさまです。
ただ、これにあきらめることなく、思いつく限りの試行・チャレンジでわたし自身の改革エンジンは止めないようにしたいと思います。
街を歩けば、ほんとうにたくさんの市民の方々が、「頑張ってほしい」と笑顔を向けてくださいます。
現在の議会状況と、市民の皆さんの期待とのあいだにはズレが大きすぎるところがあり、わたしが選挙で掲げた議会改革の内容の実現はほんとうに困難な道のりであると感じずにはいられませんが、市民の方々の笑顔はほんとうに励みとなります。頑張り抜かなければならない決意にしていただけます。
http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52277766.html
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/08/blog-post_15.html松阪市議会の体制づくり
2017年8月14日月曜日
文書質問に回答が来ました【所沢市「ところバス」の多摩湖町地域への乗り入れについて】
<東村山市議のブログより>
議会基本条例12条に基づき閉会中の文書質問を行ったところ受理され、私の質問書と市長名による回答が市議会HPにアップされました。
テキストを記事後半に掲載します。
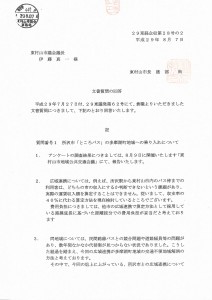
テーマは、【所沢市「ところバス」の多摩湖町地域への乗り入れについて】です。
議長と市当局の速やかな対応に感謝申し上げます。
回答書を読んでみると、明後日(9日)開かれる「地域公共交通会議」での議論が極めて重要な意味を持つことが確認できます。
交通不便地域に公共交通が整備されることに反対する人はいません。
しかし…
それが真に困っていて必要としている人たちのニーズに合致するものか、市内の他の地域の根強い要望に先んじて踏み切るべきものなのか、一旦始めたらおいそれと取りやめるわけにはいかない税金からの不足分投入は他の路線と比べて適切なものなのか…等々、事前に根拠を示した説明がなされ、地域公共交通会議でゴーサインが出され、そして議会の多数が賛同して予算化を認めるという手続きを丁寧に進めなければならないことは明らかです。
また、この回答書
明後日(9日)の地域公共交通会議は午後3時から5時の予定で、市役所6階の第2委員会室で開かれます。傍聴に出向こうと思います。
質問と回答は以下の通りです。
本年6月議会で私の一般質問に答弁いただいた点につき、直近の状況を伺います。
当市としては丁寧に検討していく旨の姿勢と受け取りましたが、本件は「所沢市のバスが乗り入れてくるものなので、現行のガイドラインとは違う手続きになる」「ガイドラインに基づかない初めてのケース」とする一方で「スケジュール的には同様」「なるべくガイドラインに沿う」とも答弁されました。市内バス路線の新規開設については、市内全域から要望の強い事項であるため、手続きの公平性や公正性、後年にわたって費用負担をすることの妥当性等、重要な論点がいくつもあります。私たち議会が判断する根拠としては、多大な労力と時間をかけて策定した「ガイドライン」と、それを踏まえた地域公共交通会議における議論が極めて重要なものとなりますが、ガイドラインの埒外であるとすれば、市民への説明責任を如何に果たすかという懸念は尽きません。また6月の所沢市議会において、本件は当市から本年4月に申し出たものであることや、極めて具体的な今後のスケジュールを示しての答弁がされています。これらを踏まえると、9月議会を待たずに現状を明らかにしていただくことが不可欠と考えています。
1.地域住民に対するアンケート調査の結果はどのようなものとなりましたか。
回答)アンケートの調査結果につきましては、8月9日に開催いたします「東村山市地域公共交通会議」にて、報告いたします。
2.「収支率40%については準拠せざるを得ない」とのことでしたが、どのような見通しになりますか。この場合の計算式はどのようなものでしょう。交通不便地域としての課題は重々承知していますが、今後への影響を考えれば、最終的には市長答弁にあるように費用の妥当性により判断することになるはずですので、算定根拠は重要と考えます。
回答)広域連携については、例えば、所沢駅から東村山市内のバス停までの利用客は、どちらの市の収入にするか判断できないという課題があり、実際に運賃収入額を算定することができません。従いまして、収支率の40%に代わる算定方法を現在検討しているところでございます。
費用負担につきましては、他市の広域連携で算定方法として採用している路線延長に基づいた距離按分での費用負担が妥当だと考えております。
3.所沢市議会6月定例議会の一般質問(6月16日)において、本件が取り上げられ、質問者は「(所沢市側から)ちょっと右側に7、8分くらい寄り道をするだけで、東村山市から費用の負担をいただき、さらには都県境を越えた住民福祉の共有、所沢駅にも行ってもらえる。いいことずくめでデメリットが全くない。どう対応するのか」と問い、答弁者は「今後も協議を重ね、乗り入れの早期実現を目指す。所沢市としての次回の路線見直しが平成30年10月予定なので間に合わせるべく地域公共交通会議に諮問を行い、今年度中には受諾できる答申をいただいて、乗り入れに向けての具体的準備を進めたい」と、後ろを切った上で、実施を前提とした答弁をしているように見えます。
所沢市としてはいいことづくめであっても、年額400万円と言われる公費負担をするのは当市であり、冷静に事業の成否を検討すべきと考えます。今後の進め方について考えを伺います。
回答)同地域については、民間路線バスとの競合問題や道路幅員等の問題があり、数年間なかなか代替案が見つからない状況でありました。こうした経過を踏まえ、今回の広域連携が多摩湖町地域の交通不便地域解消の方法と考えております。その中で、今回の俎上に上がっている、所沢市との広域連携は、両市に地域公共交通会議が設置されていることから、それぞれの地域公共交通会議で議論され、広域連携について、それぞれ合意される必要があります。
今後は、今回の需要調査の分析結果を基に8月9日に開催いたします「東村山市地域公共交通会議」にてご議論いただき、その結果を基に、具体的な対応を行っていきたいと考えております。
以上
http://sato-masataka.net/wp/?p=4142
議会基本条例12条に基づき閉会中の文書質問を行ったところ受理され、私の質問書と市長名による回答が市議会HPにアップされました。
テキストを記事後半に掲載します。
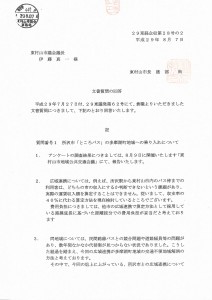
テーマは、【所沢市「ところバス」の多摩湖町地域への乗り入れについて】です。
議長と市当局の速やかな対応に感謝申し上げます。
回答書を読んでみると、明後日(9日)開かれる「地域公共交通会議」での議論が極めて重要な意味を持つことが確認できます。
交通不便地域に公共交通が整備されることに反対する人はいません。
しかし…
それが真に困っていて必要としている人たちのニーズに合致するものか、市内の他の地域の根強い要望に先んじて踏み切るべきものなのか、一旦始めたらおいそれと取りやめるわけにはいかない税金からの不足分投入は他の路線と比べて適切なものなのか…等々、事前に根拠を示した説明がなされ、地域公共交通会議でゴーサインが出され、そして議会の多数が賛同して予算化を認めるという手続きを丁寧に進めなければならないことは明らかです。
また、この回答書
明後日(9日)の地域公共交通会議は午後3時から5時の予定で、市役所6階の第2委員会室で開かれます。傍聴に出向こうと思います。
質問と回答は以下の通りです。
本年6月議会で私の一般質問に答弁いただいた点につき、直近の状況を伺います。
当市としては丁寧に検討していく旨の姿勢と受け取りましたが、本件は「所沢市のバスが乗り入れてくるものなので、現行のガイドラインとは違う手続きになる」「ガイドラインに基づかない初めてのケース」とする一方で「スケジュール的には同様」「なるべくガイドラインに沿う」とも答弁されました。市内バス路線の新規開設については、市内全域から要望の強い事項であるため、手続きの公平性や公正性、後年にわたって費用負担をすることの妥当性等、重要な論点がいくつもあります。私たち議会が判断する根拠としては、多大な労力と時間をかけて策定した「ガイドライン」と、それを踏まえた地域公共交通会議における議論が極めて重要なものとなりますが、ガイドラインの埒外であるとすれば、市民への説明責任を如何に果たすかという懸念は尽きません。また6月の所沢市議会において、本件は当市から本年4月に申し出たものであることや、極めて具体的な今後のスケジュールを示しての答弁がされています。これらを踏まえると、9月議会を待たずに現状を明らかにしていただくことが不可欠と考えています。
1.地域住民に対するアンケート調査の結果はどのようなものとなりましたか。
回答)アンケートの調査結果につきましては、8月9日に開催いたします「東村山市地域公共交通会議」にて、報告いたします。
2.「収支率40%については準拠せざるを得ない」とのことでしたが、どのような見通しになりますか。この場合の計算式はどのようなものでしょう。交通不便地域としての課題は重々承知していますが、今後への影響を考えれば、最終的には市長答弁にあるように費用の妥当性により判断することになるはずですので、算定根拠は重要と考えます。
回答)広域連携については、例えば、所沢駅から東村山市内のバス停までの利用客は、どちらの市の収入にするか判断できないという課題があり、実際に運賃収入額を算定することができません。従いまして、収支率の40%に代わる算定方法を現在検討しているところでございます。
費用負担につきましては、他市の広域連携で算定方法として採用している路線延長に基づいた距離按分での費用負担が妥当だと考えております。
3.所沢市議会6月定例議会の一般質問(6月16日)において、本件が取り上げられ、質問者は「(所沢市側から)ちょっと右側に7、8分くらい寄り道をするだけで、東村山市から費用の負担をいただき、さらには都県境を越えた住民福祉の共有、所沢駅にも行ってもらえる。いいことずくめでデメリットが全くない。どう対応するのか」と問い、答弁者は「今後も協議を重ね、乗り入れの早期実現を目指す。所沢市としての次回の路線見直しが平成30年10月予定なので間に合わせるべく地域公共交通会議に諮問を行い、今年度中には受諾できる答申をいただいて、乗り入れに向けての具体的準備を進めたい」と、後ろを切った上で、実施を前提とした答弁をしているように見えます。
所沢市としてはいいことづくめであっても、年額400万円と言われる公費負担をするのは当市であり、冷静に事業の成否を検討すべきと考えます。今後の進め方について考えを伺います。
回答)同地域については、民間路線バスとの競合問題や道路幅員等の問題があり、数年間なかなか代替案が見つからない状況でありました。こうした経過を踏まえ、今回の広域連携が多摩湖町地域の交通不便地域解消の方法と考えております。その中で、今回の俎上に上がっている、所沢市との広域連携は、両市に地域公共交通会議が設置されていることから、それぞれの地域公共交通会議で議論され、広域連携について、それぞれ合意される必要があります。
今後は、今回の需要調査の分析結果を基に8月9日に開催いたします「東村山市地域公共交通会議」にてご議論いただき、その結果を基に、具体的な対応を行っていきたいと考えております。
以上
http://sato-masataka.net/wp/?p=4142
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/08/blog-post_14.html文書質問に回答が来ました【所沢市「ところバス」の多摩湖町地域への乗り入れについて】
2017年8月13日日曜日
富山市議会 議員の賛否や議事録HP公開へ
<チューリップテレビより>
  |
(2017年08月04日 17時47分) |
http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/08/blog-post_13.html富山市議会 議員の賛否や議事録HP公開へ
登録:
投稿 (Atom)