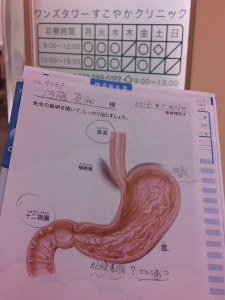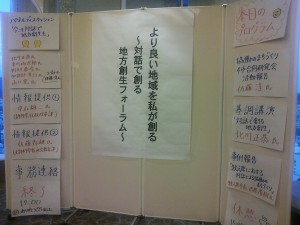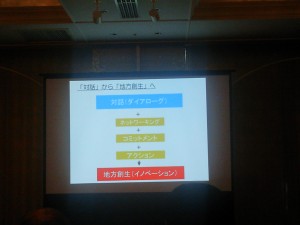女性議員が7人に・・吉川市議会
宮代町の議員選挙の2週間前に実施された、吉川市議選では無所属議員、市民ネット議員が増え議会の構成が大きく変わったと聞きました。
中でも、女性議員が7人に増えたことに注目が集まっています。
先週末、その吉川市で女性議員たちの集まり(フォーラムみたいなもの?)があり、新聞社をはじめ多くの人が集まったそうです。(すみません、私は行けなくて、あとで報告を聞きました)
私たちは、議会に女性を増やそうと「クオータ制」の導入をはじめとした様々な活動に賛同しています。女性ならではの自由闊達、柔軟な意見、ある時はマイノリティ、弱者の立場からの政策提案ができるために、政策決定の場にたくさんの女性たちが立ち会うことが不可欠だと思っています。(クオータとは、4分の1の意味ではなく、役割ということ)
が、誰でも、何でも、女性が増えればいいということではありません。(党や宗教団体などが出馬させる場合は、とにかく議員を増やすことが優先される場合が・・ないわけではない)
吉川市の集まりも、(そこん所はどうなんだろう)という気持ちも混ざってでかけた仲間議員でしたが、結果は「やっぱり、増えるってすごいこと!」 という報告でした。
吉川市の場合、当選した女性たちの多くが豊富な市民活動を経た人で、その分野が環境であったり、福祉であったりするのですが、提案や意見にキレや深みがあったというんです。
こういう人が多数を占めると議論が深くなり、また活動経験を持たない人との比較もでき、全体にレベルが上がるんだそうだ・・。なるほど。
よく、女性(男性も)議員が、経てきた肩書を列記したがりますが、こういうのが全く意味を持たないというのも、人数が多ければおいおい露呈してきますから。
やっぱり増えるっていいことなんですね。
ところで、宮代町も増えました。これまでの2倍になったということは、有権者が多様な意見の出る合議体を期待した結果でしょう。
今回の選挙で
ところで、今回の選挙では、次々にアンケート、調査、署名と称した紙が多く用いられました。とにかく、アンケート、署名・・。仕事を終わって駅の階段を下りると、階段下にずらっと並んだ運動員+候補者。(誰でもいいからゲットしよう)式の無理やりアンケート、無理やり署名にうんざりした、というのはうちの二女およびその亭主。
これに参加した人は、もうターゲット、もはや立派なシンパ扱い。そりゃー、党や団体は、ここであつめた住民ニーズをフル活用するのが目的。
「私がそれをやり遂げます」や町に対して「どうして、こんなにい多い住民ニーズを無視するのか」と大いに活用するわけ。
ある宗教(党)がいう道路の整備など、そんなに簡単に道路事情がよくなるんなら、とっくの昔にやってますって。何やら、今までの議会や執行が能なしに見えてきます。
選挙に、「あれはわが党(私)がやりました」「私なら、これができます」のアピールはつきもの。少なくとも、女性議員たちよ、生活に立脚した、正直な活動をやっていきましょう。お互いに。
お知らせ:二女の出産、身内の入院で、今日から1週間ばかり留守にします。ブログを休みます。おゆるし下さい。
http://kanou-miyashiro.blog.so-net.ne.jp/2016-02-17